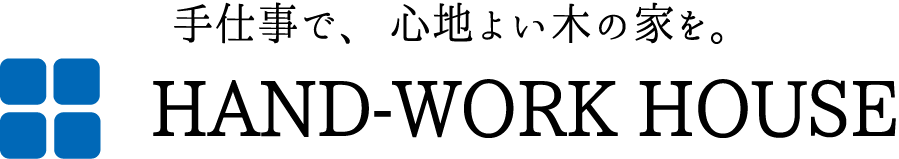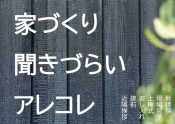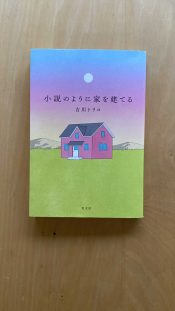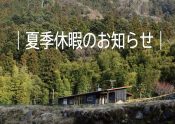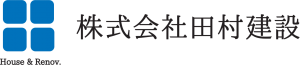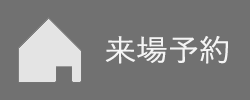カーテンをしめない暮らし -窓周りのつくり方

窓は中と外をつないでくれる、住まいに欠かせない大事なもの。
「大切なものはすべて外からやってくる」と言われるように、心地よい風も、あたたかな陽光もここから入ってきます。
だけど同時に、虫やほこり、そして人の視線も入ってきます。
なので、カーテンを引くのが当たり前。だけどそれ、本当に必要でしょうか?
ここでは「カーテン問題」について考えてみましょう。
Contents
1.窓の役割と配置計画
まず、「窓」の役割について考えてみましょう。
窓は住宅において、建物の中と外をつなぐ唯一の部材となります。
その大きさや配置によって開き方(外とのつながり方)が決まってきます。
そして、その外とつながる役割として、
1.光・熱を取り入れる
2.景色を切り取る
3.風を通す(空気を入れ替える)
4.出入りする通路
5.断熱・気密・防音
のような項目が考えられます。
4.は掃き出しの窓など人が出入りしたり、大きなものを出し入れするときに使う役割、5.は窓全体にかかる性能としての役割です。
カーテン問題に深くかかわる、「窓の配置計画」においては1.2.3.が重要になってきます。
光や熱を考える時には、太陽の通る方向と窓との関係で取り込むことのできる量が変わってくるので、窓の取りつく方角(東西南北)が大事になってきます。
景色を考えると、やはり周辺の環境、隣地の建物の位置や、道路・川・公園など開けている場所があるか、遠くに風景(山など)が見えるかなど遠近の周辺環境で決まってきます。
通風においては、方角と周辺の環境(風の通るルート)両方が影響してきます。
つまり、役割ごとに窓に求められる条件は違っており、すべての役割を1つの窓に持たせようとすることによって、矛盾が生まれ、窓をふさぐ(カーテンを引く)必要が発生してしまうのです。
ですので、窓ひとつひとつに求める役割を整理することで、ふさぐ必要の限りなく少ない窓の配置を行うことができるんですね。
もちろん、窓から見た条件をうまくクリアしても、敷地の条件からどうしても景色を楽しむ窓と外の視線が避けられないこともありえます。その時は外構計画を含めて考えていくとうまくクリアすることもできます。
2.カーテンは必要? -カーテンの役割

次はカーテンの視点からその役割を考えてみましょう。
カーテンが必要になるのはどんな時でしょうか?
A.外からの視線が気になる時(外から見られたくない窓)
B.窓の向こうに見たくないものがある時
C.まぶしい時など光を調整したいとき
D.閉めることで安心感を感じたいとき
A.B.が発生するのは、建築計画がうまくいっていない状態と言えます。
逆に言えば1章を考慮に入れたきちんとした「窓の配置計画」を行えば、ほぼA.Bが理由でカーテンを閉める必要は解消できるはずです。
逆にC.D.については、まさにカーテン類の本来の役割と言えると思います。
特に夜においては、部屋の灯りが外にこぼれることが気になったり、大きな窓から外の暗さが入り込むのに恐怖感を感じることもありますし、窓をふさぐことで精神的な安心感を感じたり、一日の終わりという気持ちの切り替えを行うという意味でも大きな役割と言えるのではないかと思います。
カーテンも決して不要なのではなく、お昼のよい時間、よいものの入ってくる時間にせっかくの窓を完全にふさいでしまうことが心地よい暮らしを損なってしまうんですね。
3.カーテンのいらない窓のつくり方
ここまで解説してきたように、窓を本来の快適な場所として使うには、道路や隣家を考慮した配置計画が最も大切です。
景色に対して大きく開きたい窓は、遠くまで視線の抜ける場所に配置することで、より広がりを感じることができます。
敷地によっては景色のよい方角が北向きの場合もあるかもしれません。それでも景色を楽しむ窓はそれでいいんです。光や熱を取り込む役割は他の窓に担ってもらいましょう。
しかし、この景色を楽しむ窓が、どうしても道路方向に向いてしまうこともままあります。そんな時には、外構を一緒に考えてみましょう。
例えば道路と窓との間に少し高めの木製フェンスをたて、その内側に木を植えてみましょう。すると、視線を遮りながら程よく囲われた庭が生まれ、プライベートな雰囲気のお庭と一体になった窓辺が生まれます。
歩行者の視線も木々の緑に注意が向くので、より外の視線が気にならなくなります。
道路がすぐ近くて庭のスペースが取れないときは、格子網戸やルーバーで視線をぼかす方法があります。
カーテンだと視界をすべてふさいでしまいますが、これを使えば、視線をある程度遮りながら、光や外の景色を取り入れることが可能です。
また、窓に障子を付けることも方法のひとつです。
障子は景色を見ることはできませんが、光を取り込み、和紙がその光を柔らかく拡散してくれることで、とても優しい雰囲気の空間が生まれます。
窓の役割の話をしましたが、どんな条件のところでも、すべての役割を放棄するのではなく、建築的な工夫によって、ひとつでもその役割を保持できるように考えると、せっかくの開口部が無駄になりません。
このように建築的な操作によって、限りなくカーテンをしめなくてよい、開放的な窓辺をつくることで、より心地よい日常を送ることができるんですね。
4.窓の活かし方 -カーテン(遮蔽部材)の種類
一口にカーテンと言いましたが、窓をふさぐ部材にはいろいろな種類があります。
その窓に求める役割やふさぎ方を考えて、どの遮蔽物を採用するか考えると、より窓が生きてきます。
|カーテン …しっかりと窓をふさぐことができる。厚手のものは断熱性能も高い。横に開く。
|レースカーテン …薄手のもので光を通しながら視線をカットできる。ひらひらとなびき、風を感じることができる。
|ブラインド …スラットが建横のもの、縦のものがある。角度を調整することで、入る光を調整することができる。鋼製、木製と素材も豊富。
|ロールカーテン …しっかりと窓をふさぐことができる。縦方向に稼働するので、半分開けたりという調整がやりやすい。
|ハニカムブラインド …ロールカーテンのように縦に稼働する。和紙っぽい雰囲気があり、断熱性が高いのが特徴。
|障子 …伝統的な遮蔽建具。取付には基本鴨居敷居(レール)の部材が必要。光を柔らかく拡散する。
|格子 …窓の外、または内に取り付ける部材。外の視線や日射を程よく遮りながら、光や風景を取り込むことができる。網戸と一体になったものもある。
開き方によって使い方がずいぶん変わってくるので、この窓はいつも全部閉めるか、半分くらい開きたいとか、日差しが強いので光を調整したいとか、使い方をイメージして選ぶことがポイントです。
また、トイレや脱衣室などの小さな窓ではカーテンを付けないことも多いですし、外の視線や夜の闇が気になるのであれば、ガラスの種類を透明ではなく、「型ガラス」と呼ばれる半透明のガラスにすることも選択肢のひとつです。型ガラスは半透明で向こうの景色がぼんやりとしか見えないので、採光の役割だけを持たせるにはうってつけのガラスです。
5.プラスα 心地よい窓周りのつくり方
ここまでカーテンを中心に窓周りのつくり方を解説してきましたが、窓周りは住まいの豊かさを決める大きな要素です。窓周りはカーテンを閉めなくてよい、開放感を味わえる場所、外からくるよいものを楽しめる場所として、できるだけ心地よいつくりにしたいものです。いくつか事例を中心に解説をしたいと思います。
|開放的な窓辺、ベンチを添えて
外部とつながる大きな窓のそばにTV台と一体になったベンチを設けました。
窓のそばに座れる場所があると、より外を身近に感じることができます。ベンチの下はしっかり収納にもなっています。
|ウッドデッキとつながるフルオープンできる開口
ウッドデッキとつながる窓は3.2mのフルオープンできる窓にすることで、ウッドデッキとリビングを一体として使えるダイナミックな空間に。屋根をかけることで、雨の日も外遊びをすることができます。
|太陽を取り込むインナーバルコニー
窓辺をサンルームのようなちょっと囲われた空間に。床の仕上げを変えることで、太陽の熱をたっぷり蓄えることができる暖かな空間になりました。
|コーナー窓+タタミ

コーナー窓と呼ばれる建物の角にL形に窓を配置した形式。2方向に開口が来ることで、大きな解放感と外への連続感が生まれます。
窓の高さを下げ、タタミの床と組み合わせることで、窓のそばに腰を下ろし、風景を眺めることができる心地よい窓辺が生まれます。
6.まとめ
窓は、外からやってくる光や風、景色といった「心地よいもの」を暮らしに届ける大切な存在です。
しかし、配置や役割が整理されていないと、せっかくの窓もカーテンで閉ざされ、機能を十分に活かせなくなってしまいます。
建築計画の段階で窓の役割を明確にし、視線や環境を考慮した工夫を加えることで、昼間はカーテンを開け放ち、自然を感じながら暮らせる空間が生まれます。
また、カーテンやブラインド、障子などの選択肢も、遮るだけでなく光や風をコントロールし、心地よさを高める重要な道具となります。
「窓を活かす」ことは、日常をより豊かにすること。カーテンを閉めることが前提の暮らしではなく、開放的で快適な窓辺づくりを目指すことで、住まいはぐっと心地よい場所へと変わっていきます。
家づくりの際には、「窓周り」を大切に、しっかりとイメージして計画を進めましょう。
【無料メルマガ 登録のススメ】
HAND-WORK HOUSE|田村建設 では、様々な家づくりにまつわる情報を、無料メルマガ【家づくり通信】にて配信しています。
週に一度を目安にメールにて皆様にお送りしておりますので、家づくりにご興味のある方はぜひ読んでいただければと思います。
登録はメールアドレスのみで簡単に登録できますので、下のリンクからお願いいたします。