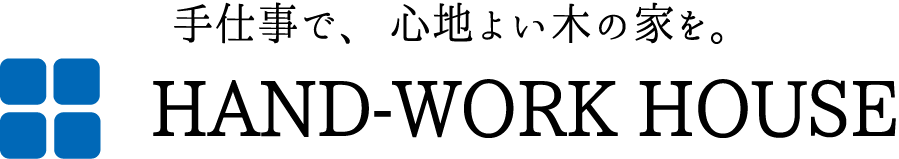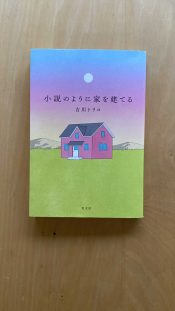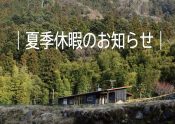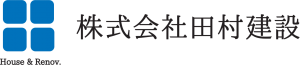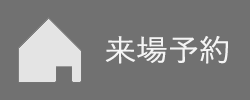Q&A| 家づくりの際の、聞きづらいアレコレ
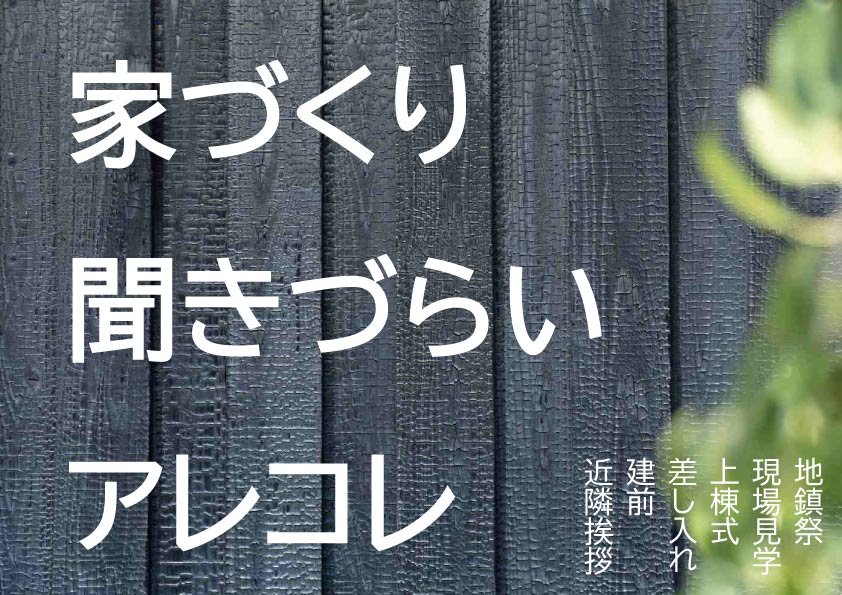
長かった計画期間を経て、契約も無事おわり、いよいよ家づくりが始まる!という時、ワクワクがいっぱいな半面、「家づくりって、わからないことだらけで不安になる…」そんな声をよく耳にします。
地鎮祭の準備、ご祝儀、差し入れ、近隣挨拶など、「誰かに聞きたいけどちょっと聞きづらいこと」って意外と多いですよね。
こうした疑問を放置して進めてしまうと、思わぬトラブルや後悔につながる可能性があります。せっかくの家づくりがストレスになってしまうのは本末転倒です。
本記事では、各儀式の準備や現場でのマナーなど、「聞きにくいアレコレ」をすべて一冊にまとめたような内容で解説をいたします。地鎮祭やご祝儀といった儀礼的なことから、現場見学や差し入れのマナーなど、実践的なアドバイスを凝縮しています。もちろん、地域差や、それぞれの施工者・職人さんとの関係性もありますので、明確な正解はありませんが、ひとつの目安として参考にしていただければと思います。
家づくりは大きな決断と長い準備が必要ですが、正しい情報と準備があれば、その過程も楽しみに変わります。この記事を通じて、不安を「安心」に変え、理想の家づくりを実現しましょう。
Contents
工事前のアレコレ についてのQ&A
Q0| 近隣住民の方への挨拶と配慮
A. 工事前に挨拶へ参りましょう
家づくりも立派な建築工事。規模は小さいとはいえ、どうしても騒音や車両の出入りで近隣の方への負担がかかります。
お家が完成して住み始めた際には、近隣の方々は文字通り「ご近所さん」になる人々です。引っ越し後の良好なご近所関係を気付くためにも必ず工事前にご挨拶へ行きましょう。
ご挨拶が着工後になると、不要なトラブルを起こす可能性がありますので、必ず着工前にご挨拶に行くよう心掛けてください。
ご挨拶の範囲は、その土地の条件によっても変わりますが、概ね両隣や後の3軒、お向かいの3軒くらいでしょうか。
場所によっては、その土地の代表の方に挨拶する方が良い場合もありますし、前面道路が複数のお家で共用となっている場合には関わるお家すべてに挨拶に行くことが必要になります。
土地に詳しい方や、工務店とよくお話して範囲を決めると良いと思います。
また、工務店でも挨拶に行かれることが多いので、それぞれで伺うか、一緒に伺うかもご相談されると安心です。
ご挨拶の際の手土産にはタオルや洗剤など日用品が無難です。高価なものは必要ありません、気持ちを表すことが大切です。
ご挨拶の際には、自身のお名前や工事期間、工事を担当する工務店名などをお伝えすると良いと思います。
後ほど工務店の方で挨拶に伺う際にスムーズになります。またその際に工事期間や作業時間、緊急連絡先などを記した案内文をお渡しすることで工事の周知を行います。
引き渡し後も改めてお礼を行い、入居後の良好な近所付き合いにつなげましょう。
儀式の日のアレコレ についてのQ&A
Q1| 地鎮祭の準備物は何が必要?
A. 基本的にはお供え物と玉串料(初穂料)を用意します。
地鎮祭は、工事の安全を祈願する大切な儀式です。
近年では省略するケースもあると聞きますが、家づくりのスタートとなる節目としてぜひ実施していただきたい儀式です。
神主さんにお願いする神式、お坊さんにお願いする仏式など、いくつかの形式があります。
地域や神社、お寺によって準備物が異なる場合があるため、お願いする神社やお寺、または工務店さんに事前に確認いたしましょう。お供え物としては海と山の幸を取り混ぜ、米・塩・酒・魚・野菜・果物などが一般的です。これらは五穀豊穣を象徴し、工事が円滑に進むことを祈る意味があります。
玉串料は3〜5万円程度が相場で、封筒には「御初穂料」または「玉串料」と記載し、施主名を入れます。
テントや祭壇などは施工会社が準備することが多いですが、供物台などを施主が用意するケースもあります。施工会社との打ち合わせで役割を確認しておきましょう。
Q2| 地鎮祭の服装は?
A. 当日の服装は決まりはありませんが、清潔感ある服装が望ましいです。
動きやすさを考慮し、靴はヒールやサンダルを避けることをおすすめします。
地鎮祭は実際の家づくりを始める最初の一歩。家づくりの思い出のアルバムの最初を飾るイベントです。
皆さんにとっての「家づくりのスタート」にふさわしい服装をご準備いただければと思います。
Q3| 建前(柱建て)の日はどうしたらいいの?
A. 家づくりの醍醐味です。組みあがっていくわが家をぜひ体験してください!
建前(柱建て)は大勢の大工さんで一気に木の骨組みを組み立てていく、家づくりの中で最も華やかな工事になります。
工法や規模にもよりますが、1~2日であっという間に家のカタチができてくるのは、なかなか壮観な眺めです。
一日中でなくてもよいので、ぜひご家族でこの日ダイナミックな瞬間を体験してもらえると良いと思います。
2日かかる場合もあり、毎日時間をとるのはさすがに難しいこともあると思いますので、工務店さんと相談してみる日を決めるのもよいと思います。
工務店さんによっては、朝一番の一番柱をたてる作業をお施主さんにお願いしたりと、参加型の建前をおこなうところもあります。
建前はおおむね1日いっぱいの時間がかかるため、時間にはシビアです。
一般的に作業は8時ちょうどにスタートするので、工務店さんとよくお話をして参加の際には時間に遅れないように注意しましょう。
A. お昼ご飯の準備をお願いしています。
建前は大工さん、レッカーさん、ガードマンさん、工務店のスタッフさんなど、大人数で行う一大工事です。
チームでの作業がとても大切で、みんなで同じ食事をとることは、チームワークを育くみ、良い仕事をスムーズに行う上で大きな役割を果たしてくれます。
職人さんにお昼ご飯の心配なく作業に集中してもらうため、また、お施主さんにもチームの一員として参加してもらう意味でも、昼食の用意をお願いしています。
少し人数が多くて大変だと思いますが、一緒に家づくりに参加していただければと思います。
Q4| 上棟時の大工さんへのご祝儀
A. 決まりはありませんが、大工さんのモチベーションにつながります。
上棟式は、お家の骨組みが完成したことを祝う、大工さんにとっても、家づくりにおいても大きな節目となる行事です。ここまでの大工さん・職人さんの仕事への感謝を表し、その先の工事の安全と完成を記念する場です。
ご祝儀を用意するかは決まりはありませんが、ここには上棟までの仕事をねぎらう意味と、完成までよろしくお願いしますという激励の意味も込められることになります。
建前(柱建て)はその先も仕事をしてくれるそのお家の担当の大工さんと、建前の時だけお手伝いに来てくれる大工さんが参加してくれています。
担当の大工さんを「棟梁」と呼ぶことが多く、棟梁の仕事がその家の出来栄えを左右すると言って過言ではありません。
特に、大工さんや職人さんがお施主さんに直接お会いする機会は少ないので、面と向かってご祝儀を受け取った大工さんには、大きなモチベーションが生まれます。
やっぱり人間ですから、誰かも知らない人の家をつくるよりも、顔を知っている人の家をつくる方が、「あの人のために!」と気持ちが入りますよね。
ご祝儀の相場は棟梁に1〜3万円、他の職人さんに5千円〜1万円程度が一般的です。
最近ではご祝儀の代わりにお土産として、飲み物などを用意するケースも増えています。形式よりも感謝の心が大切です。
工務店さんによってご祝儀の考え方もあるかもしれないので、地域性と現場の慣習を尊重することも踏まえ、ご祝儀を渡したいむねを事前にお話しておくとよいでしょう。
また、上棟式を建前(柱建て)の日の夕方に行う場合と、その後日を改めて行う場合があるので、どちらでご祝儀を用意すればよいかも事前に相談されると安心です。
工事中のアレコレ についてのQ&A
Q5| 工事中は現場見学に行ってもいいの?
A. 安全に気を付けて、しっかり見てください。
一歩ずつ完成に近づいていく過程を見ていくことも、家づくりの醍醐味のひとつです。
時間が許せば、様々な工事の状況を観察してみてださい。
しかし、住宅の工事現場には、電動のこぎりやノミなどの刃物など危険な道具や材料も使用されています。
特に小さなお子様の居られる方は安全に注意して見学することが重要です。
足元には釘や資材が落ちていることもあるため、サンダルやヒールは避け、動きやすい靴を履きましょう。
現場では勝手に資材や配線には触れないようにしましょう。ケガをしたり、資材の破損につながる場合があります。
職人さんは午前10時や午後3時に短い休憩をとることが多いので、その時間を絡めて見学したりと、職人さんの負担にならないように配慮すると喜ばれます。
特に危険な作業のある日などもあるので、見学に行く際には、事前に施工会社や現場監督に連絡を入れるようにするとよいでしょう。
見学のルールについては、事前に工務店さんや現場監督に確認しておくと安心です。
Q6| 工事中の職人さんへの差し入れはいるの?
A. 職人さんにたいへん喜ばれます!
工事中の差し入れは必須ではありませんが、とても喜ばれる習慣です。夏場や冬場は飲み物が特に助かります。
夏は冷たいスポーツドリンクや麦茶、冬は温かいお茶や缶コーヒーが好まれます。現場には紙コップや湯沸し器を常備するところが多いので、大型のペットボトルや、お湯で溶かせる飲み物など手軽に飲めるものが重宝されます。
お菓子は個包装されたものが安全です。職人さんによっては小食の方もいらっしゃったりするので、少しずつ手軽に口にできるものが無難です。
職人さんは、午前10時や午後3時に短い休憩をとることが多いので、差し入れのタイミングはこの時間がありがたがれます。
作業の妨げにならない時間になりますし、職人さんも心置きなく話ができるので、お施主さんとの会話も弾みます。ぜひ度々差し入れにいらしてください(笑)
まとめ
お施主さんからしばしば聞かれる家づくりにおけるアレコレについて整理してみましたが、参考になりましたでしょうか?
どの質問にも、決まった正解があるわけではありませんので、ここに挙げた内容を基本としながら、関係各所と相談して確認していただければと思います。
ひとつ言えるのは、近隣の方も、大工さん・職人さんも、工務店のスタッフも、みんな同じ人間だということです。
ですので、送った気持ちには、気持ちが返ってきます。
それを考えて行動すれば、きっと良いお家につながると思います。
また、家づくりに関する新しいアレコレが出てきましたら、この記事に追記していきたいと思いますので、その時はまたご参考ください。