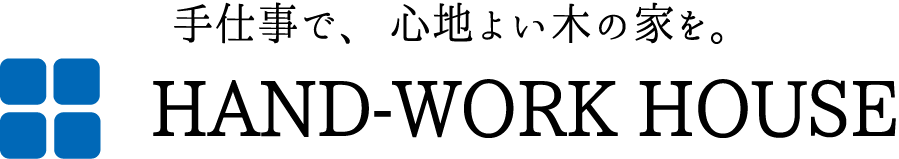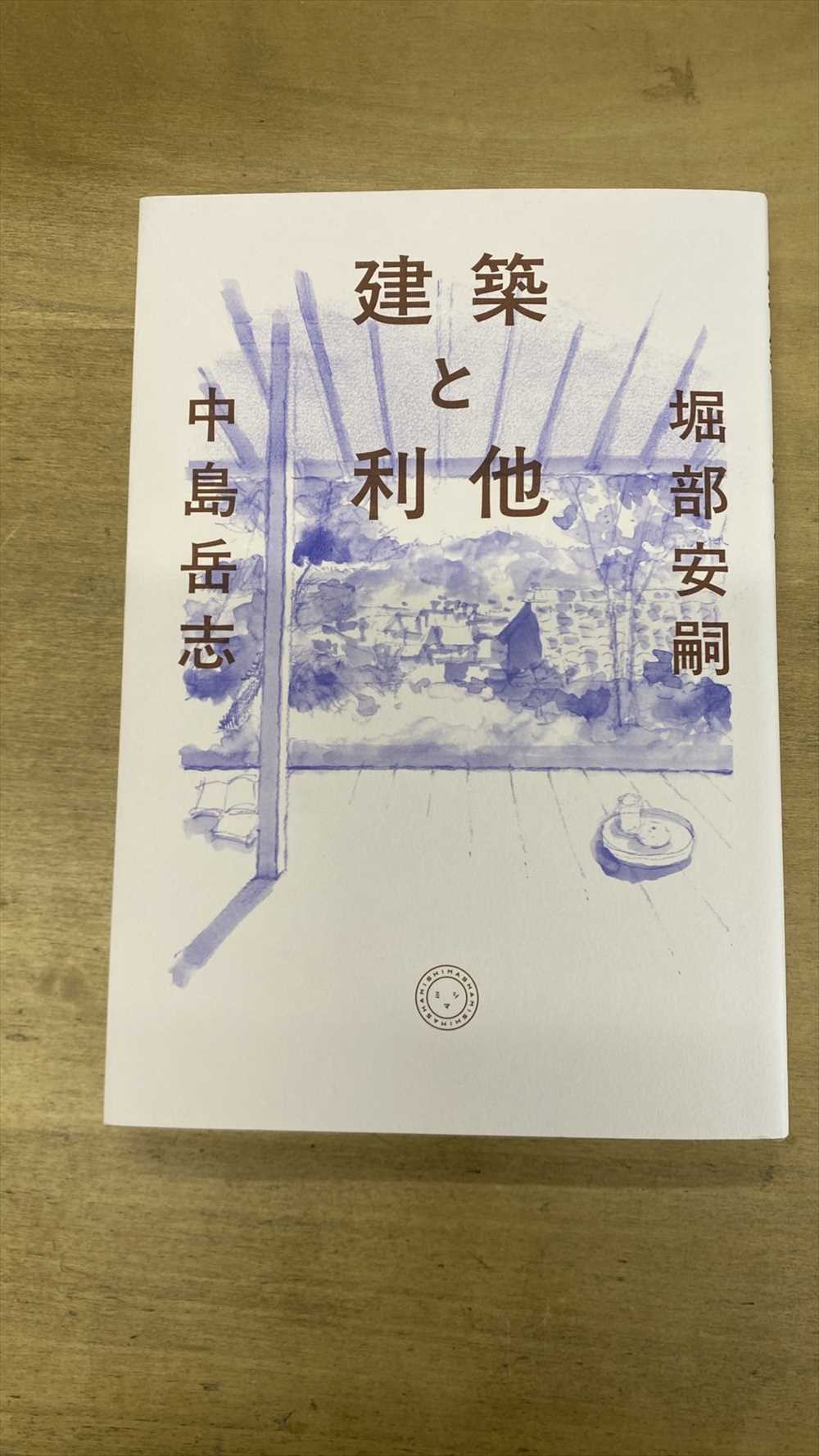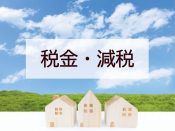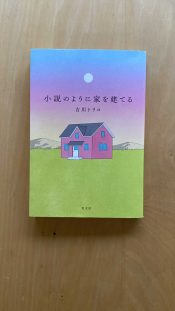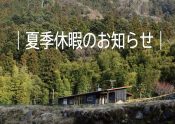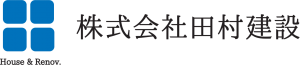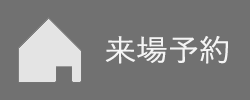パッシブデザインを考える
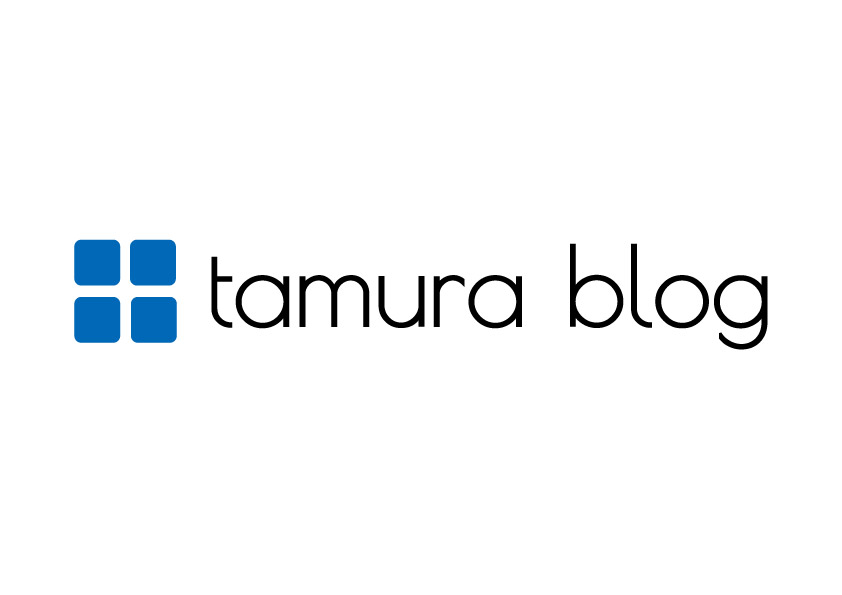
こんにちは。
HAND-WORK HOUSE|田村建設
代表の田村です。
先日、建築家/堀部泰嗣さんの著書「建築と利他」を読みまして、パッシブデザインについて考えるところがありましたのでか、つづってみたいと思います。
「パッシブデザイン」とは、一般的に機械設備に頼らず、太陽光・風・熱といった自然エネルギーをうまく活かして、室内の温熱環境を快適に保つ設計手法のことを指します。建物は一定の場所に固定されるものですから、その建物の置かれた場所の周辺に存在する自然の力をうまく見極め、上手に暮らしの中に取り込むことがこのパッシブデザインの要ですね。例えば南側に大きな窓をもうけて、冬に太陽光をいっぱい取り込み、太陽の熱の力で部屋を暖める。夏に庇で太陽光の侵入をさえぎり、窓をいくつも配置して風の流れをつくり、風を通して涼を取り込む。これらは決して新しい考え方ではなく、伝統的な日本住宅では当たり前に取り入れられていた考え方です。
「家は夏を旨とすべし」という言葉を聞いたことがないでしょうか。
昔はエアコンなどはないですから、冬は火をたいて暖を取ることができましたが、夏の暑さが暮らしの最大の障害でした。ですので暑さをうまく乗り切る工夫が住宅に求められました。そこで活用されていたのが【パッシブデザイン】。大きな庇を出して太陽光の室内への侵入をふせぎ、大きな開口部で【通風】を徹底的に行う。まさにパッシブデザインの基本ですね。逆に昔はパッシブデザインだけで家の快適性をつくっていたわけですから、その工夫は今も見習わなければならないものがあります。
さて、堀部さんは著書の中で「(その土地に)すでにあるものに、抵抗するのではなくて、それを活かしてというか、条件を受け入れていくというのでしょうか、そういうことが僕は広義の意味で【パッシブデザイン】だという風に考えています」と述べられています。
これを読んでハッとしたのですが、そこにあるものを受け入れる(取り入れる)というのは、なにも〈自然〉だけじゃないんじゃないか。そこにある建物や道やなにか、人が生み出したものも同じように扱うべきなんじゃないか。そう思いました。
そう考えると、お隣のお庭を<借景>として取り入れたり、風情ある地域の街並みを景色として取り入れたり、という今まで認識せずやっていたことも、実は【パッシブデザイン】のひとつなのかもしれません。

住宅が建つためには必ず敷地があり、その周辺の条件が必ずついてきます。
『自然の力だけでなく、周辺の建物、すべての条件を上手に活用して、住まい手の心地よい暮らしをつくる設計手法』がバージョンアップした【新時代のパッシブデザイン】なのかもしれませんね。
もっともっと意識して【パッシブな暮らし】を考えて行きたいと思います。