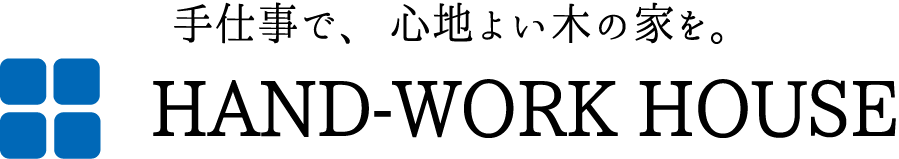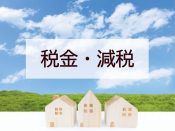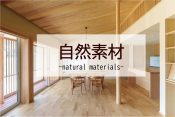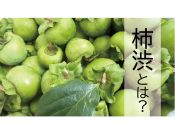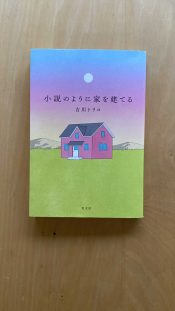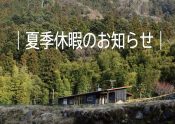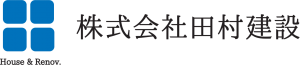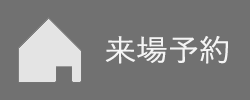暮らしの灯りを見つめ直す
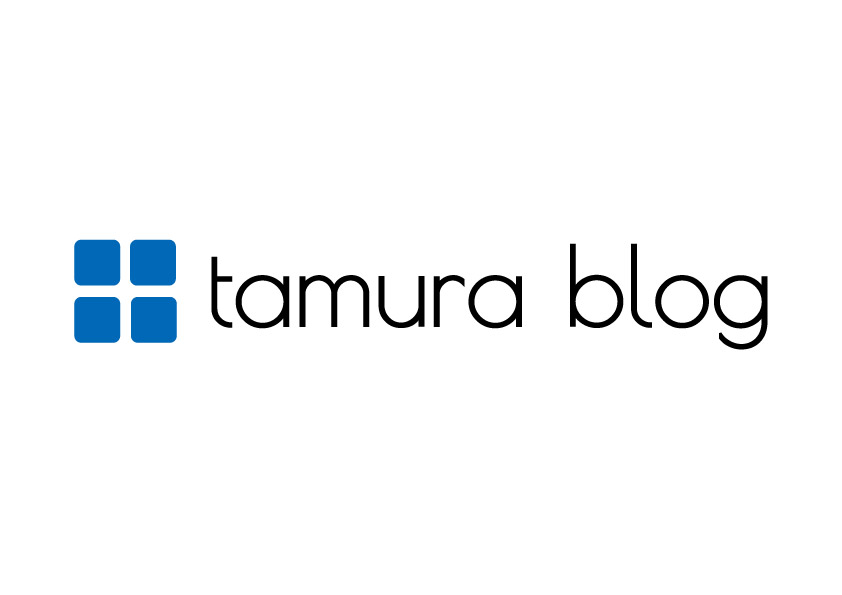
暮らしの灯りを見つめ直す ― 照明計画でつくる、落ち着きとくつろぎの住まい
照明は現代の住まいにおいて欠かすことのできない存在です。夜というかつて生活の外にあった時間を、有効な生活時間に変えてくれる、人類の素晴らしい発明ですよね。
しかし、現代において住宅における「照明」は、単なる明るさの確保のためだけにあるものではありません。それは空間に「余白」を与え、住まい手の気持ちを穏やかにし、日々の営みに寄り添うように、そっと寄り添う「空気のような存在」であるべきだと、私たちは考えています。
照明は、光そのものだけでなく、「暗さ」や「影」とどう向き合うかというデザインでもあります。今回は、煌々とした人工的な明るさから離れ、「ほのかな灯り」がもたらす本質的な心地よさについて、私たちが家づくりのなかで大切にしている視点をお伝えしていきます。
| 明るければ良いという思い込みを手放す
私たちは「明るい家=良い家」と思い込みがちです。モデルハウスや展示場では、どこもかしこも天井にびっしりとダウンライトが並び、影すら感じないほどの照明計画がなされています。一見「美しく整っている」と感じますが、そこには暮らしの陰影も、心を落ち着ける余白もありません。
実際の暮らしでは、すべての空間が常に明るくある必要はありません。例えば夜のリビング。家族でテレビを見たり、静かに本を読んだり、くつろぎの時間を過ごすには、全体が明るすぎるとむしろ疲れてしまうのです。
ほのかな間接照明や、スタンドライトの柔らかい光が、人の心をゆるめ、空間に深みを与えてくれます。
| 天井照明を減らして、灯りの重心を下げる
私たちが提案する照明計画では、天井に極力照明器具を設けません。代わりに、ブラケットライト(壁付け照明)や、ペンダントライト、スタンドライトなどを組み合わせ、空間のあちこちに「灯りの居場所」を散りばめていきます。
その理由のひとつは、光の重心を低く保つこと。照明が高い位置から降り注ぐと、空間全体が平坦に感じられます。しかし、灯りが腰高や床に近い位置からやさしく広がると、落ち着いた雰囲気が生まれ、空間に陰影と奥行きが生まれます。
これは、和の住まいに通じる考え方でもあります。提灯や行灯に象徴されるように、日本人は古くから、足元に近い灯りのぬくもりに心を寄せてきました。その伝統を、現代の暮らしにふさわしいかたちで取り入れていきたいと考えています。
| 必要な場所に、必要なだけの光を
すべてを均一に照らすのではなく、暮らしの動線や用途に応じて、必要な場所にだけ灯りを届ける。この考え方が、結果として住まいにとっても、住まい手にとっても「ちょうど良い」照明環境を生み出します。
たとえばキッチンでは、手元を明るく照らすペンダントライトやライティングレールを使います。ダイニングでは、テーブルの上だけをほんのり照らすようにし、周囲は暗くても問題ありません。キャンプの時、焚火の周りにみんなが集まるように、住宅においてもテーブルを照らす灯りにつられて、自然とダイニングに家族が集まるのです。寝室や廊下は、夜の静けさを邪魔しないよう、光量は抑えめに。フットライトのように足元だけを照らすのも良い選択です。特に寝室は眠りに向かう場所、生活空間よりも小さな灯りで身体を眠りに向かってより落ち着かせていくことで、よりスムーズに快適な睡眠を得ることができます。
「必要なところに、必要なだけ」を心がけることで、エネルギーの節約にもつながります。
| 器具は「控えめ」で「空間の一部」であること

照明器具そのものも、できるだけ主張のない、シンプルなデザインを選びたいところです。空間の中で目立たず、あくまでも「引き立て役」になるような存在感が理想です。
建築家 吉村順三さんは「照明器具が欲しいのではなくひかりが欲しいのだ」と仰ったと言います。照明器具はその姿を消し、灯りだけが残るような、灯りのついていない時でも、空間の静けさを乱さないような照明器具を考えます。
私たちが選ぶのは、陶器や真鍮、木など自然素材を使った照明器具。ペンダントライトのコードはなるべく細く、器具の色は壁や天井に馴染むように調整します。ブラケットライトもデザインは極力シンプルにし、「灯り」そのものの美しさを引き立てるように心がけます。
そうすることで、住まいの素材やしつらえが主役になり、照明はその舞台を静かに支える名脇役になります。
| 暗さを楽しむという贅沢
夜の暗さは、決してネガティブなものではありません。むしろ、暗さがあるからこそ、灯りが美しく感じられるのです。
ほのかに灯るブラケットライトの陰影。スタンドライトが照らす床の色や質感。これらは、明るさでは得られない「静けさ」や「温もり」を住まいにもたらしてくれます。
「陰影礼讃」という言葉がありますが、まさにその通り。陰と陽、明と暗があってこそ、空間には表情が生まれます。
暗がりの中に身を置いて、心を鎮める。そんな時間があるからこそ、私たちは日常の喧騒から解放されて、「暮らす」という営みに立ち戻ることができるのです。
| 照明計画は、最後ではなく最初に考える
多くの方が、照明は家づくりの最後の方に考えれば良いと思いがちです。しかし、本当に心地よい照明計画を実現するためには、設計初期から灯りの位置と種類を意識することが重要です。
窓の配置や壁面の素材、家具のレイアウトとも密接に関係します。私たちは設計段階から、自然光と人工照明のバランスを丁寧に読み解き、「暮らしのシーン」に寄り添う灯りの演出をご提案しています。
その結果、住まい全体が自然体で心地よく、夜が待ち遠しくなるような空間が生まれます。
| 照明が導く、ていねいな暮らし
毎日の暮らしは、慌ただしく過ぎていくもの。だからこそ、家に帰ってきたとき、灯りがそっと心をほぐしてくれるような住まいであってほしい。
照明は、暮らしのテンポを整え、季節や時間帯に寄り添いながら、住まい手に静かな「リズム」を与えてくれます。
無駄に明るくするのではなく、灯るさに「余白」を残す。
それが、私たちが大切にしたい照明のあり方です。
このような考え方に共感していただけたら、ぜひ家づくりの際には、「どんな灯りに包まれて暮らしたいか?」という視点で、照明計画を楽しんでいただけたらと思います。